既に存在しないWebコンテンツにも、無くなるには惜しいページがある。
誰かの都合のみが理由で、たまたま、無くなっていくのだろうけれど。
ネット上にごく少数点在するアーカイブサイトで、いつ本当になくなるとも分からないコンテンツの中に、以下のようなものを見つけた。
本来は、著作権めいたものが存在するのだろうけれど、これがあった読売新聞のサイト内には、すでにこの記事はないのだから、捨てたものを私が拾って、惜しいから残しておいたとしても、誰も叱る人はいなかろうと思い、転載する。
10月2日12時30分頃、姪が帝王切開で出産したと、病院に付き添っている弟から電話をもらった。
その日は朝から出かけていた母親の帰宅を待って、病院へ母と向かったのは午後2時30分頃となった。
病院の3階のエスカレーターの近くのフロアーにあるソファーと机のところにいる弟夫婦と落ち合った。
すぐに、弟に連れられて姪の病室へ様子を見に行った。
声をかけるとまだ麻酔が抜け切れていなくて、もうろうとしているようで、焦点の定まらない目でこちらを見たが私のことはわかったようだった。
姪の横にはなぜか赤ん坊がいなかった。
戻りながら弟に聞くと赤ん坊は緊急治療室にいるのことあった。
ソファーの所に戻ると、その後すぐに姪の亭主が緊急治療室から戻ってきた。
われわれの顔を見るなり、ふいに、涙を浮べた。
それを見て、われわれは駄目なのかなと一瞬息を飲んだ。
それから、姪の亭主は気を取り直したようにソファに座って、医師から説明を受けてきた症状を何通かの書類と、一枚のポラロイドに撮られた赤ん坊の写真を机の上に並べながら説明を始めた。
弟夫婦と母は真剣に耳を傾けていた。
私には遠くの世界のことのように、ほとんど何を言っているのか理解できなかった。
いつもポーカーフェイスの姪の亭主の涙を見たのと、ポラロイドに写った保育器に入った赤ん坊の口にチューブがものものしいのと、何通かの書類の文字がかなり難しい漢字の羅列であることからこれはただならない症状だなというのは察しがついた。
赤ん坊には午後6時にならないと面会出来ないということなので待つことにした。
病院内の喫茶店へ行ったりして時間をつぶし、時間が来て、緊急治療室に向かった。
しかし、治療室の中には姪の亭主しか入れないということで、われわれはガラス越しに面会をしている姪の亭主の行動を見守ることとなった。
頭に布をかぶり、手を洗い、青の病院服を着るのに時間がかかった。
赤ん坊の保育器は奥の方にあって、ガラス越しのわれわれのの方からは死角のところにあって足しか見えな状態だった。われわれのすぐ手前には喉の当たりにチューブを入れられた女の赤ちゃんの頭を、愛おしむように何回も何回もなでているお父さんの姿があった。
ちょっと不良っぽい感じの人だったがその姿はまさに親そのものだったが、こんなことから人はだんだん親になっていくのだろうなとそのときふっと思った。
その後、治療室を出て、出入り口付近の机のところで担当医師に図解を交えながら説明を受けた。
それも私にはよく解らなかった。
面会を終えて、とりあえずわれわれは家へ戻ることにした。
一緒に食事をしようということでいったん弟夫婦、姪の旦那と一端別々に帰宅した。
そして我が家の前の中華料理屋で食事をしながら、姪の旦那が、担当の医師に元気の出る名前を決めて下さいと言われたということで、すでに命名事典を書店から購入してきていて、すでに検討した跡があってあるページが折られていた。
そのページを示しながら「康太」にしようと思いますと言った。
われわれは好きなように名前を付けることを奨めていたので、反対することもなくすぐにそれに決まった。
とりあえず名前も決まりホッとしてその日は解散した。
家に帰り、さすがに長時間病院にいたのはこたえたようで、テレビを見るでもなく、半分寝ながらごろごろとしていた。
私より先には寝床に入らない母が珍しく先に寝るよと言って床についた。明日早くから出かけるのだからと別に気にもとめなかった。
そのあと、すぐ私も風呂に入ってから自分の部屋に戻った。
時間にして翌日の0時15分頃だった。
私もいつもよりずっと早くの寝床入りとなった。
枕元のスタンドの明かりで読書を始めるかいなか、電話がけたたましく鳴った。
それは弟からで、
「赤ちゃんとみんなで記念写真を撮りたいからデジカメを持ってすぐ病院へ来てくれ」
ということだった。
何か胸騒ぎを感じ、取るもとりあえず、着替えてから、机にあったデジカメと財布、家の鍵を持って玄関まで行くと、母親がパジャマ姿で起きてきて、どうしたの?と聞くので、「デジカメでみんなと赤ちゃんと写真を撮ってと電話があったから」と説明して玄関を出た。
家の前にちょうど止まっていたタクシーに飛び乗って病院へと駆けつけた。
その間20分だった。
昼間とは違って、夜の病院は緊急出入り口の灯りがポツンと見えるだけで妙に寂しい。
守衛に事情を説明してエレベーターで3階まで行った。
廊下の電気は切られて、緊急治療室の灯りだけがポツンと見えた。
弟たちはどこにいるのかわからないので、とりあえず緊急治療室の入口でインターホーンで場所を聞くことにした。
すぐに、担当医師がやってきて私を裏の廊下の隅の方の薄暗い灯りのところに案内をしてくれた。
そこには、移動用のベッドに寝かされた姪の周りに、弟夫婦と姪の亭主が赤ちゃんを抱っこしてそれぞれがのぞき込んでいた。
さっそく私はデジカメのスイッチを入れ、まず、赤ちゃんを囲んだ姪夫婦を2枚撮った。
そして姪の亭主が抱いたのを2枚、それから弟の嫁さんが赤ちゃんを抱いたのを2枚、弟が抱いたのを2枚とたてつづけに撮った。
笑いながら抱っこした弟の眼鏡の奥は涙で濡れていた。
そして、私が抱っこするのを姪の亭主が2枚撮ってくれた。
当然首が座っていないのでおっかなびっくりの抱っことなった。
わずかな重さがこの世に生を受けた赤ちゃんの実感として伝わってきた。
顔をのぞき込むと生まれて間もないのに本当に端正な顔つきをして可愛いかった。
それから、また姪の亭主に抱っこされたのを一緒に2枚。
そのあと姪のベッドに横たえ、服から手足を出して、姪と2人でのショットを連続して追った。
最初は赤ちゃんの顔をのぞき込んで笑顔の姪であったが、こらえきれなくなって唇をきっと結び、涙が頬を伝わった。
そして赤ちゃんをぎゅっと腕に抱え、その状態でしばらくじっとしていた。次から次へと涙が頬を伝う。
ここまで来ると撮りながらもらい泣きをしてしまった。
そして、担当の医師が来てお別れというところで、姪は赤ちゃんを最後の頬ずりを泣きながら何回もしていた。
これには私も頬を痙攣させるしかなかった。
大事に赤ちゃんを抱えて担当医師は緊急治療室の方へと戻っていった。
そのあと、姪は一般病室へと移ることとなって、われわれは看護婦の先導のもとに7階の個室へと移動した。
そしてその日は姪の亭主が付き添いでとまるということで、弟夫婦の車に同乗して家へ帰った。
翌日は、私は出席しなかったのだが、病院の霊安室で、特別に姪も車椅子で、病院にいる看護婦全員が康太君のために焼香をしたということだった。
死因は、右側の横隔膜に穴が開くという奇病で、そこから羊水が体に流れ込み、肝臓など内臓が上半身に押しやられて、そのため肺が発達せず通常の10分の1ほどしかなかったということだった。
康太くんは、一度も声を発することなく、そしてその目を開いて我々の顔を見ることなく、わずかに手足を動かしただけで、半日の命であった。
まさに、こんにちわ、そしてさようなら。
とはいうものの、抱っこの思い出と、我々には何とも言えない愛しい思い出を残してくれた。
わずかなこの世のであったが、間違いなく康太君は10ヶ月の間お母さんと一心同体であった。
康太君が苦しんでいるとき、母親も本当に苦しんで大変だった。
それぞれの抱っこは、それぞれの自分自身を伺うものであった。
そして、我々の命というのは、危ういバランスの上に成り立っていることを思い、そしてこうして育った我々がいるという奇跡のような、よくぞ育ったものだという感銘を改めて思う。
五体満足というのはどういうことなのだろうか。
生において五体満足が実態のないものであるかということを強く思う。
むしろ、どこかしらなんらかの欠陥があって普通なのではないのかと思った。
その方が余計命の愛おしさを実感するのだ。
往生要集ぐらいは、もっと普通に読まれても良いだろう。
そして、病院でのこのケアでよいと思う。
翌日、この病院での撮影したものをロールプリントアウトをして、この写真の流れを見ながら改めて涙が止めどもなく流れた。
姪の痛みを思う。
昼間は、小さな棺のなかには姪の一番好きだったぬいぐるみだけと、周りにわずかな花だけであったのが、通夜には、棺の中に、白い靴、キャンデー、ガラガラ、そして沢山の花束が。
火葬場に行くころにはおしゃぶりも加わった。
火葬場で最後にほっぺたを指でさわったらまだプリンとしていた。
ちゃんと戒名もついた。
これは、儀式的なものなのだが、康太君の生に一つの形を与えた。そして我々もそれで気持を治める。
康太君のこの世に思い出として残したものは、少々の髪の毛と、今にも崩れそうな遺骨。
何故に康太君はこんなに早く逝ってしまったのか。彼は、モンディウス言うところの「一来果」なのだろう。もう地上に戻らなくてもいい人なのかもしれない。
康太君は、もちろんかって生まれ死んでいった人から生まれた。
彼の生まれてきた背景を考えるとそういうことになる。
彼は、病院で生まれ病院で逝った。
それも私の父が死んだ同じ病院で。
改めて、病院の空間性と場所そして、その背後の連続性を思う。
地上は思い出ならずや。
愛は惜しみなく奪う。
2002年10月2日は、私にとって当分は忘れることは出来ないだろうし、もしかしたらひとつのターニングポイントになるかもしれない。
それは、正確には10月3日午前0時30分頃だ。

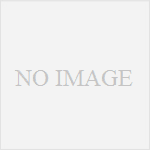
コメント